SCATの30周年
※メッセージの所属・役職はSCAT 設立30 周年当時のものです。
SCATの歩み
1982~1987(昭和57~62)
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
| ― |
|
1988(昭和63 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
1989( 平成元 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
1990( 平成2 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
1991( 平成3 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
1992( 平成4 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
1993( 平成5 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
1994( 平成6 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
1995( 平成7 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
1996( 平成8 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
1997( 平成9 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
1998(平成10 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
1999(平成11 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
■7月1日 NTTが持株会社化、東・西日本、長距離分離
|
2000(平成12 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2001(平成13 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
■4月1日 独立行政法人 通信総合研究所(CRL) 発足
|
2002(平成14 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2003(平成15 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
□4月1日 日本郵政公社が発足
□10月1日 NASDA・ISAS・NAL統合、(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)発足
|
2004(平成16 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
■4月1日 (独)CRLと(特認)TAOが合併し(独)情報通信研究機構(NICT)が発足
|
2005(平成17 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2006(平成18 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2007(平成19 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
□10月1日 郵政民営化スタート
|
2008(平成20 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2009(平成21 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2010(平成22 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2011(平成23 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2012(平成24 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2013(平成25 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2014(平成26 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2015(平成27 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
□4月1日 NICTが独立行政法人から国立研究開発法人に移行
|
2016(平成28 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2017(平成29 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2018(平成30 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
2019(平成31/令和元 )
| SCATの主な活動状況 | 社会・経済等の主な出来事 |
|---|---|
|
|
メッセージ
創立30周年おめでとうございます 一般財団法人 テレコム先端技術研究支援センター 代表理事・会長 安田 靖彦

一般財団法人
テレコム先端技術研究支援センター
代表理事・会長 安田 靖彦
テレコム先端技術研究支援センターは、1988年10月に郵政大臣より財団法人設立許可を得て武田豊氏を初代会長として発足しました。
その後、私が代表理事・会長に就任した年である2008年の『公益法人制度改革関連三法』全面施行を受けて、当センターは内閣総理大臣より認可を得て2012年4月に一般財団法人に移行しており、今年、2018年10月に設立30周年を無事迎えます。
これもひとえに情報通信技術分野等の関係諸機関の皆様方の御厚情とご支援の賜物と感謝申し上げます。
当センターは、設立以来、情報通信技術分野における先端的な技術に関する調査研究とその支援、国際共同研究に関する支援、先端技術情報の提供などの事業を通じて、我が国の情報通信技術の研究開発の進展に向け力を尽くして参りました。
現在、三法のうち通称『整備法』第119条の公益目的支出計画に定める、当センターの『公益目的事業』は、教授・准教授等の大学研究者に対する①「研究助成事業」と一般向けの②「技術情報及び知識の普及事業」ですが、センターの全事業に占める公益目的事業比率は、一般財団法人移行後平均60%以上で推移しております。
②「技術情報及び知識の普及事業」の一環として1989年より開始した、各分野の専門家が講演し、どなたでもご聴講いただける「テレコム技術情報セミナー」は、2017年に合計100回を数えております。
①「研究助成事業」の一環として1991年より大学等の研究者に対する「研究費助成」を開始し2015年に合計300件を超え、続いて1992年より博士後期課程在学者に対する「研究奨励金」を開始し2008年に合計100件超の実績を積み上げてきました。さらに、1993年より国際交流促進のため「国際会議助成」を開始し2015年に合計400件超に達しております。間接費を除く助成金累計総額は、助成開始25年後の2014年度までに、NTT・KDDから寄付された当センター指定正味財産46.5億円の1/3相当額を超えております。
また、設立以来、関係諸機関の御要望にお応えし、『共益事業』として、「超高速フォトニックネットワーク開発推進協議会(PIF)」「アジア情報通信基盤共同研究会(AIC)」「ネットワークロボットフォーラム(NRF)」「高度言語情報融合フォーラム(ALAGIN)」をはじめとする15を超える任意団体の事務局を引き受けてきました。
この他、『収益事業』として行政庁や研究機関からの委託を受け、「生体電磁環境」、「周波数有効利用技術」「衛星通信システム」「インキュベーションズ」等多岐にわたる分野に係る調査研究等を実施して参りました。
創立30周年という節目にこのような当センターの活動の歴史を振り返り、後世への記録として整理・保存することは、関係の皆様の当センターに対する御理解を深めていただく一助になると考え、『30年の歩み』を刊行することといたしました。
本誌の編纂に際し御支援御協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げるとともに、関係諸機関の皆様方の今後益々の御発展と御多幸を祈念いたします。
当センターでは、引き続き公益目的事業等を通じて、我が国の産業の強靭化と国民の安全・安心に資するICTの発展に向けて尽力して参りますので、今後とも皆様方の御支援・御協力をお願い申し上げます。
創立30周年おめでとうございます 一般財団法人 テレコム先端技術研究支援センター 評議員 羽鳥 光俊 (東京大学名誉教授)

一般財団法人
テレコム先端技術研究支援センター
評議員 羽鳥 光俊
(東京大学名誉教授)
一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター(SCAT)創立30周年誠におめでとうございます。
私のSCAT とのご縁は、平成20年(2008年)安田靖彦先生がSCAT の代表理事会長に就任されて空いた評議員の空席に入れていただいたことに始まります。
SCAT は昭和63年(1988年)、財団法人として設立され、約30年にわたり、先端的な情報通信技術に関する調査研究及びそれに対する支援並びに先端的な情報通信技術の国際共同研究に関する支援を行うとともに、情報通信技術の研究開発に関する知識の普及、振興、提言等の事業を行い、広く情報通信技術の研究開発の推進に寄与し、もって我が国社会経済の発展に貢献されてきました。
SCAT は、設立直後に郵政省から「電気通信フロンティア研究開発」を受託して研究開発を行われたのをはじめとして、その後、郵政省/総務省、CRL から「情報通信ブレークスルー基礎研究21」の受託、総務省から「戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)に関わる事務」の受託、その他多くの調査研究・支援事業の受託を手掛けてこられました。
中でも、皆様御承知のSCOPE は平成14年度(2002年度)から開始された総務省の情報通信分野の研究のための競争的資金で、若手研究者等に大変喜ばれている事業です。その応募案件審査を実施される先生方を裏から支援する事務事業は非常に意義のある仕事と思いますが、SCAT では、平成14年度(2002年度)~平成21年度(2009年度)、平成25年度及び平成27年度の通算10ケ年度の長きにわたり、総務省から受託し適切に実施してこられました。
また、SCAT では、このSCOPE に11年先駆けて、平成3年度(1991年度)から財団法人による情報通信分野の競争的資金として、「大学への寄付金」等の形式をとる「研究費助成」を実施されている他、大学院博士後期課程在学者に対する「研究奨励金」の支給、学会等への「国際会議助成」を行うなど、着実かつ継続的に公益目的事業に取り組んでこられました。
その他、ICT分野の先端技術の研究開発の産学官連携のために創設された多数の任意団体の事務局運営も積極的に引き受けて来られました。
SCAT は、平成24年(2012年)に一般財団法人への移行、平成26年(2014年)に公益目的支出計画変更認可を乗り越えて今日を迎えられたわけですが、評議員としては、これらの対応には関係者の大変なご苦労とご努力があったと承知いたしております。特に、乏しい運用益等財源の中で公益目的支出計画の最適化を図るべく、当初の公益目的支出計画の実施期間33年間を新計画で倍の66年間に延長する計画変更につき、ICT関係一般法人で初めて内閣府より「整備法」上の認可を受け、課題となっていた赤字、即ち正味財産の減少に歯止めをかけました。さらに、同年9月には内部規則を改正し実施事業収入の解消を行い、公益目的財産残額の減少ロスを大幅にカットする「軽微な変更」を行い、財団経営状態の改善が図られました。
今後ともゼロ金利・マイナス金利が続く場合、金融財産運用益等で公益目的事業等の経費を賄うSCAT の財政状況は大変苦しく、業務執行のご苦労は絶えないとは存じますが、評議員としてはSCAT が関係機関から変わらぬご支援を得て、永く我が国のICT研究開発に貢献することを祈念いたします。
大きな変化を乗り越えて ~SCAT 創立30 周年に寄せて~ 総務省 総務審議官(郵政・通信) 鈴木 茂樹

一般社団法人テレコム先端技術研究支援センター(SCAT)創立30 周年、真におめでとうございます。
私が郵政省に入省したのは昭和56 年のことですが、それから約37 年、現在に至るまで通信・放送・郵便分野は激変の連続でした。通信の自由化とNTT の民営化、衛星放送の導入、全郵便局のオンラインネットワークの導入、インターネットの普及とブロードバンド化、携帯電話の普及と情報通信端末化、省庁再編、郵政事業の民営化・分社化、地上テレビジョン放送のデジタル化、IoT・ビッグデータ・AI など、そうした大きな変化を乗り越えて、通信・放送・郵便分野は大きく発展してきました。
特にSCAT が設立された昭和63 年は、電気通信事業の自由化の3年後であり、電気通信市場への多くの事業者の参入と競争の促進による激変の最中でした。このような大波の中で生まれたSCAT が、情報通信技術(ICT)の中でも特に先端的な研究開発の支援という、いわば「種を播く」仕事に、永きにわたり取り組んでこられ、その成果として新たなサービス・財が生まれてきたことは、まさにSCAT に関係する皆様のご尽力の賜であり、心より感謝申し上げます。この30 年の成果は、現在の我が国の先進的なICT 環境の礎になっているとともに、播かれた種はこれからも多くの花を咲かせることでしょう。また、このような研究支援やSCATを中心とした数々の協議会活動は、現在のICT 社会の原動力となり、優れたICT 人材の輩出にも貢献していくと認識しております。
現在、一人一台の携帯端末の時代を経て、モノとモノがつながるIoT(Internet of Things)という新しい時代を迎えております。このような状況の中、我が国は、少子高齢化の進行による労働力不足が経済・社会の停滞をもたらす懸念を抱えております。このような課題の解決に向けて、IoT、ビッグデータ及びAI の活用に対する期待が日に日に高まっているのを感じます。総務省としても、これらの技術革新による新たなサービスの出現や産業構造の変革を促進し、我が国の持続的な経済成長を実現するための取組を進めて参ります。そのためにもSCAT を含む関係者の皆様方のお力添えが必要でありますので、引き続きご協力のほどお願いいたします。
SCAT は、30 年目という一つの節目を迎えましたが、これからも40 年、50 年と、ICT の速い変化に柔軟かつ迅速に対応することにより発展していくことを楽しみにしております。SCAT 及び関係者の皆様の今後益々のご活躍を祈念して、設立30 周年のご挨拶とさせていただきます。
SCAT創立30周年、その先へ 総務省 総務審議官(国際) 富永 昌彦

この度は、一般社団法人テレコム先端技術研究支援センター(SCAT)が創立30 周年を迎えられたとのこと、誠におめでとうございます。情報通信技術(ICT)は、国民生活や産業を支える様々な技術の中でも特に進展のスピードが速く、社会から要請される研究のテーマもダイナミックに変化するという状況の中で、長期的な視点に立ち、一貫して最先端の技術研究に対する支援に取り組んできていただいた関係者の皆様には並々ならぬご苦労があったことかと存じます。あらためて感謝申し上げます。
SCAT が設立された昭和63 年は、NTT の民営化の3年後であり、電気通信の研究開発をめぐる状況が大きく変化する中で、政府の科学技術政策において基礎研究重視の姿勢が打ち出されるなど、研究開発における国と民間の役割というものが強く意識された時代でありました。
同時期に、郵政省の電波研究所が通信総合研究所に改組され、また、超高速通信技術、高機能ネットワーク技術及びバイオ・知的通信技術の3分野を中心とする「電気通信フロンティア研究開発」プロジェクトがスタートするなど、基礎研究に対する取組が強化されましたが、このような国が自ら行う研究の強化に加えて、SCAT には先端的な情報通信技術の研究活動の支援や大学院博士後期課程進学者に対する支援など、我が国のICT 分野における研究活動や研究人材の層を充実させる取組を進めていただきました。
それから30 年。今日では、様々な分野においてIoT、ビッグデータ、AI といったICT の活用が期待されており、これらICT により、私たちの生活、ビジネス、経済・社会に大きな変革がもたらされようとしています。政府や産業界においても、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く新たな社会としてSociety 5.0 が提唱されており、科学技術によるイノベーションの先導の下、サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合の実現を目指していますが、その中でもICT は中心的な役割をしっかりと果たしていくことが期待されています。
我が国は、今後、人口減少を始めとする様々な課題を抱える中で、より豊かな社会へと持続的に成長していくことが求められていますが、このためには、あらゆる分野においてICTを活用していくことが非常に重要となります。我が国が、ICT の分野において世界最先端であり続け、国際競争力を維持し続けられるよう、ICT 分野の研究開発に関連するコミュニティには大きな期待がかけられています。SCAT 及び関係の皆様の今後のますますのご活躍を祈念し、創立30 周年のお祝いの言葉といたします。
SCAT創立30周年に寄せて 国立研究開発法人 情報通信研究機構 理事長 徳田 英幸

国立研究開発法人 情報通信研究機構
理事長 徳田 英幸
一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター(SCAT)が創立30周年を迎えられましたことを心よりお慶び申し上げます。
皆さまご承知のとおり、情報通信は、縦に分かれた個々の技術分野の一つであるというよりは、あらゆる分野と融合し、横への連携を促進し、社会経済活動の基盤を支える重要な技術分野となっています。私ども情報通信研究機構は、我が国唯一の情報通信分野を専門とする公的研究機関として、基礎的・先端的な研究開発から、具体的な技術の社会実装に向けた技術実証や、ベンチャービジネスの支援などの振興業務など、幅広い業務に取り組んできたところです。近年では、IoT、ビッグデータ、AI などの技術進歩により、サイバー空間と我々の身の回りの物理空間の融合が加速し、より安全・安心な社会インフラの構築や新しい価値を創出するコネクテッドサービスの実現を可能とする情報通信技術の研究開発やその社会実装が重要であり、情報通信研究機構に求められる役割も大きく変わってまいりました。
特に、社会経済の様々な分野において情報通信技術を活用した新たな価値創造を実現するためには、国、地方公共団体、大学、民間企業等による密接な相互連携を通じ、さまざまな分野の利用者を巻き込んだ広範なオープンイノベーションを創出することが必要です。情報通信研究機構においても、研究開発成果を最大化するため、産学官のネットワーク形成や共同研究の実施、大学等との連携の強化、産学官連携の取組としての協議会の設立・運営等、とりわけオープンイノベーションの創出に向けた取組に力を入れております。
こうした状況にあって、SCATにおかれては、設立以来、幾多の研究支援や助成の事業や先端的な技術に関する調査研究に取り組みつつ、オープンイノベーションの概念を先取りし、永らく情報通信分野の先端的な研究開発に携わる産学官の関係者のネットワークのハブとしての役割を果たされてまいりました。情報通信研究機構と関係の深いところでは、超高速フォトニックネットワークや、全く新しい設計思想・技術に基づいた新世代ネットワークの創出に向けた取組においては、関係協議会・フォーラム活動の事務局としての役割を担い、新しい技術の実現に向けた関係者の協調・連携に多大な貢献をされてこられました。
また、私個人にとりましても、2003年に設立されたネットワークロボットフォーラムの会長を務めておりましたが、同フォーラムが2014年に次世代ロボット開発ネットワーク(RooBO)と合併してアイ・ローボ・ネットワーク・フォーラムとなるまでの間、その活動を事務局として支えてくださいましたのがSCATでございました。今でこそネットワーク技術とロボット技術の融合によるネットワークロボットという概念はごく自然なものとしてとらえられますが、設立当初は、かなり突飛なものとしてとらえられることすらあった状況で、フォーラムの設立当初は世界的にも先端的なシステムコンセプトでした。そうした中で、SCATにおかれては、これからまさに芽吹こうとする先端的な技術にいち早く着目され、標準化を含む海外機関との連携、動向調査や標準化活動に向けた議論など多方面において関係者の支援になみなみならぬご尽力をいただきました。情報通信分野の研究者の一人としても、深く感謝をするところであります。
近年では、ネットワークロボットは、サイバーフィジカルシステムにおける構成要素の1つとしてより重要な役割を担っており、新しい社会インフラの構築にとって必須なシステム技術となっています。このようなサイバー空間とフィジカル空間が融合した新しいサイバーフィジカル空間を支える情報通信技術の研究開発や社会実装を推進していくためにも、SCATにはぜひこれからも研究支援の場で大きな役割を果たしていただきたいと願っております。関係事業に多くの成果が実りますことを祈念いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。
大変革時代を乗り越えるために ~創立30周年に寄せて~ 日本電信電話株式会社 代表取締役副社長 篠原 弘道

日本電信電話株式会社
代表取締役副社長 篠原 弘道
この度は創立30 周年をお迎えされたこと、誠におめでとうございます。30 年もの長きに渡り、情報通信技術の発展だけでなく社会経済の発展までを目指した先端技術への研究助成事業や、各種情報発信・啓蒙活動等によって培われた数多くの実績は、この業界における大きな財産になっているものと確信しており、通信事業者に身を置く一人として厚く御礼を申し上げます。
さて、近年の情報通信産業を取り巻く環境は、全く新たなプレイヤーが革新的な製品やサービスをグローバルに展開するなど急激なパラダイム変化が生じており、この先もより多種多様な技術が急速に拡がる可能性を秘めています。さらに、我が国のあるべき姿として政府が掲げた「Society 5.0(超スマート社会)」では、AI、IoT、ビッグデータ、サイバーセキュリティ等の情報通信技術が社会課題を解決するシステムをつなぐ基盤技術として位置づけられ、産学官の緊密な連携のもとで研究開発から社会実装までの取組が加速されようとしております。このような大変革時代を迎えた今、情報通信技術の研究開発に携わる者を一貫して元気づけてこられた貴センターへの期待は、これまで以上に高まるのではないでしょうか。
ところで、大変革時代を我が国が一体となって乗り切るためには、二つの方向性によって情報通信技術を深化させていくべきではないかと考えています。まず一つ目は、情報通信技術そのものを究めるというものです。貴センターが取り組まれている研究助成事業は先端的な研究活動の支援を目的とされておりますが、この営みによって新たなゲームチェンジを萌芽するような破壊的イノベーションの種が数多く創出されることを期待してやみません。さらに、たとえば、我が国が世界で大きなアドバンテージを持つ光通信分野の研究開発を産学官で推進する「超高速フォトニックネットワーク開発推進協議会」を事務局として支えられているように、ある目的のもとに世界と戦うために集う関係者の結束を、より強固なものとしていただくことにも引き続き取り組んでいただければ大変心強い限りです。
つぎに、情報通信技術の利活用幅を拡げるという方向性も重要といえます。課題先進国である我が国は、数多くの課題を情報通信技術の利活用によって世界に先駆けて解決することが至上命題となっています。そのためには技術を適用する現場からの要求条件を明確にし、その条件に合致するようカスタマイズしながら社会実装へと導くことが必要ですが、社会実装の過程では、これまで情報通信技術との関係が薄かった分野の方々やエンドユーザの方々に技術を正しく理解していただく「社会受容性の醸成」についても考慮する必要があります。貴センターが取り組まれているような情報提供・知識普及事業はその一端を担えるのではないかと考えておりますし、ここで得た知見を整理して関係省庁に提言することも大変有意義ではないかと思います。
末筆になりますが、貴センターが大変革時代を乗り越えるためのキープレイヤーとして益々ご発展されることを心より祈念いたします。
SCAT30周年おめでとうございます。 株式会社KDDI総合研究所 代表取締役会長 公益財団法人KDDI財団 理事長 渡辺 文夫

株式会社KDDI総合研究所 代表取締役会長
公益財団法人KDDI財団 理事長
渡辺 文夫
一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター(SCAT)創立30 周年、誠におめでとうございます。
1985 年のNTT の民営化と電気通信事業の自由化により、日本の情報通信環境が大きく変化したことを受け、SCAT は1988 年に設立され、1992 年までにNTT とKDD から出資された基財産をベースに活動されてきました。当時の経緯は本記念誌に詳しい訳ですが、諸先輩・関係の皆様の営々たる努力の積み重ねで、情報通信分野における今日までの活動成果があること、この分野の一員として感謝いたすしだいです。
私、公益財団法人KDDI 財団の理事長も務めており、一般財団法人のSCAT と似た分野において似たような立場の活動を行っており、野津専務理事をはじめ関係の皆様の御苦労も如何ばかりかと拝察します。SCAT では、「公益目的事業」として、「研究助成事業」や「技術情報及び知識の普及事業」を、「共益事業」として、情報通信関連の数多くの任意団体の事務局を務め、さらに、「収益事業」として行政や研究機関からの委託調査研究等を実施されています。
ゼロ金利時代に至り、公益目的事業等の経費を基本財産の運用益で賄う財政は大変苦しいものになります。一定以上のリスクがある運用はできない中、様々な工夫で財団経営状況の改善を図り、財団活動全体の維持向上をされています。
情報通信産業は、各種産業分野の中で最大と言われる規模となり、他の産業の成長を促す存在となり、またモバイルサービスを典型として日常社会生活に深く浸透して正に社会の基盤となっています。今後も、5G、IoT、ビッグデータ、AI と言ったICT により、経済・社会・ビジネスに留まらず、私たちの生活の大きな変革が期待されるところです。こうした「超スマート社会/Society 5.0」に向けては、独創的でイノベーティブな研究開発とその社会実装が必須です。産学官が連携してグローバルな視点で活動していくことが必要です。
SCAT は、情報通信分野の先端的な研究開発に携わる産学官のネットワークのハブとしての役割を長く果たしてきました。より豊かな社会へと持続的に成長していくためには、直近の研究技術開発のみならず、10 年後20 年先に大きく花開く可能性にチャレンジすることや、将来を担う若い世代の活動をこれまで以上に重視していく必要があると考えられます。
SCAT の関係事業に多くの成果が継続的に実りますことを祈念いたします。
設立30周年に寄せて テレコム先端技術研究支援センター 前会長 熊谷 信昭 (大阪大学名誉教授)

テレコム先端技術研究支援センター
前会長 熊谷 信昭
(大阪大学名誉教授)
テレコム先端技術研究支援センターが設立された昭和63 年当時、私は大阪大学総長在任中で、郵政省電気通信フロンティア研究推進委員会の委員長なども務めていました。そして、平成3 年に大阪大学を退官した後も、兵庫県立大学長や総務省マルチメディアバーチャルラボ開発推進協議会の会長や郵政省情報通信ブレークスルー基礎研究21 推進会議の会長などのほか、総務省独立行政法人評価委員会の委員長などを務めていましたが、平成15 年4 月に当センターの会長を拝命し、平成19 年3 月まで4 年間務めさせていただきました。
その間も、独立行政法人科学技術振興機構運営会議会長など色々な仕事をさせていただきましたが、まことに幸いなことに、これら多くの役職を務めていくにあたって、深刻に悩んだり、大変な苦労をしたような記憶は全くありませんでした。それは、情報・通信技術を含む先端的な科学技術の研究・開発に対する当時の政治や行政や経済界などの深いご理解と暖かいご支援が非常に大きかったお陰であったと思います。
なかでも特に強く印象に残っているのは、平成7 年11 月に「科学技術基本法」という世界的にも他にあまり例をみないユニークな法律ができたことでした。この法律は衆参両院とも自民党から共産党まで全会派の満場一致で成立した画期的な法律で、その第一条では「我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与するとともに、世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な発展に貢献することを目的とする」という高い志が謳われています。そして、その第三条で、「国は、科学技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する」と定めて「国の責務」であることを明記し、また、その第九条では「政府は、科学技術会議の議を経て、科学技術の振興に関する基本的な計画(科学技術基本計画)を策定しなければならない」と具体的に義務づけています。
科学技術会議(現総合科学技術・イノベーション会議)というのは、内閣総理大臣を議長とする内閣直属の重要な審議機関の一つで、政府の科学技術に関する基本政策について審議する会議として昭和34 年に設置され、私は平成5 年12 月から平成12 年12 月まで7 年間その議員を務めていましたが、その在任中にこのような画期的な法律が成立したことに感無量の思いがしました。
この法律の成立をうけて、我々科学技術会議では平成8 年度から平成12 年度までの5 年間に国が講ずべき科学技術に関する重要な施策について検討し、必要な予算規模等まで具体的に書き込んだ「科学技術基本計画」(第一期)を作成しましたが、その中には、例えば、政府は平成8 年度から向こう5 年間に総額17 兆円の科学技術振興関連経費を投入すべきこと、などが具体的に明記されています。そして実際、この(第一期)「科学技術基本計画」で示された重点施策と予算計画はその後の5 年間の計画期間内に確実に実行されたのです。当時の政府の対応はまことに立派であったといえると思います。
私は科学技術会議の議員として、第一期の科学技術基本計画の策定とその推進にかかわり、第二期の基本計画の原案をまとめて次に引き継いだわけですが、科学技術の研究・開発をめぐる当時の我が国の政治や行政の雰囲気がそのような情況であったお陰で、私が会長を拝命していた間も、当センターの事業を円滑に進めていくことが出来たのではないかと思っています。
もっとも、実際に実務を遂行するにあたっては事務局の方々やご関係の皆様方には様々なご苦労をおかけしていたはずで、この機会に改めて深く感謝の意を表したいと思います。
本当に有難うございました。
テレコム先端技術研究支援 センター創立30周年に寄せて テレコム先端技術研究支援センター 研究助成審査委員会 元委員長 堀内 和夫 (早稲田大学名誉教授)

テレコム先端技術研究支援センター
研究助成審査委員会 元委員長 堀内 和夫
(早稲田大学名誉教授)
テレコム先端技術研究支援センター創立30周年をお祝い申し上げるとともに、創立当初から今日に至るまでの関係者各位の御尽力に、心から敬意を捧げるものでございます。
下って、私事、情報通信システムの関数解析的数学理論の開発研究に日々を過ごして参りましたが、その間にもお会いできた多くのすぐれた先輩方のおひきたてにより、幾つかの社会的なお仕事の流れに身を置くことができたのは、誠にしあわせでした。中でも、このセンターの中で過ごすことができた20年は、生涯の中で正に大きなエポックでした。
身近な先輩として、かねがね兄事してきた猪瀬 博先生が、このセンターの研究助成審査委員会(以下、本委員会という。)の初代委員長をつとめておられた間、そのかたわらで委員長代理として、先生のお姿から常々学ばせて頂いたすべてが、先生のあとを引き継いだ2代目委員長の私の姿でありました。
実際には、まず、研究助成審査専門部会(以下、専門部会という。)が分野毎の精細な審査を進め、得られた詳細な審査結果が、辻井重男専門部会長から本委員会に報告されます。それを原案として、本委員会は、委員長司会のもとに、相磯秀夫委員長代理、辻井重男専門部会長をはじめとする委員の皆さんによって精細な審査を進め、更に総合的な判断のもとに決裁します。
毎年、本委員会による厳格な審査を経て本センターの研究助成を受けられた研究者の皆さんには、皇居前のホテルの一室で会食を共にしながら助成の手続きをすませたのですが、現役の活力に満ちた皆さんの姿に接するのが、研究者であることを自負している老人にとって、誠に嬉しいひとときでありました。
研究助成審査活動を振り返って 一般財団法人 テレコム先端技術研究支援センター 研究助成審査委員会 前委員長 辻井 重男 (中央大学教授、東京工業大学名誉教授)

一般財団法人 テレコム先端技術研究支援センター
研究助成審査委員会 前委員長 辻井 重男
(中央大学教授、東京工業大学名誉教授)
創立30周年、おめでとうございます。この間に、SCAT がテレコム先端技術研究の振興に果たされた貢献は、非常に大きいものがあったと研究助成の審査を担当した立場から実感しています。助成金額は、政府系の大型プロジェクトなどに比較すれば、多くはありませんが、萌芽的、挑戦的研究の推進には大いに役立ったのではないかと思います。
私も含め多くの研究者が、「現在の政府系プロジェクトの研究助成のあり方が続けば、20年後には、日本からはノーベル賞は出ませんよ」と小さな声で言って来ましたが、研究者仲間にしか聞こえませんでした。同じことを昨年のノーベル賞受賞者、大隅博士が大きな声で、訴えておられるので、日本の研究助成が悲観的状況にあることに対する社会的認識も多少は深まったかと思います。
研究助成金が活用されるためには、2つの視点が重要です。1つは、言うまでもなく金額の多寡です。もう1つは、与えられた助成金を、自由な発想に基づいて使用出来るかと言う点です。前者の重要性は言うまでもないことで、研究者でない方にもご理解いただけることでしょう。問題は、研究費を柔軟に活用できるかどうかです。研究費の会計処理や、報告書作成などに多くの時間を割かれ、研究効率が落ちないかと言う点です。研究は、「異分野との自由な発想に基づく連携や、研究申請書に記入した当初計画に対して、より高い成果を生めるような柔軟な変更が可能」と言うような、ある種のつながり文化の中で、予期しない成果が得られたりします。これに対して、会計は、時間の効率を軽視する切り分け文化です。
私がある国立大学に努めていた頃の昔話を一つ。未だ、成田空港がなく、羽田空港からヨーロッパまで、アラスカ経由で、15時間くらいかかった頃のことです。パリで開催される2つの国際会議に日曜日を挿んで出席することになりました。前半の出張旅費は、A省から、後半はB省から出ました。大学の事務職員、真面目な顔で曰く
「先生、1時間でいいから、一旦、羽田へ戻ってくれませんか」
流石にそれは勘弁してもらいましたが、笑い話ではなく、会計処理の筋論から言うとそういうことになるのでしょう。
SCAT の場合、当初から、研究文化が尊重され、情報通信分野で、多くの成果が生まれたことは誇りに出来ると思います。
今後、ビッグデータ、AI、IoT などの進展普及により、人と情報の交わる環境をどう構築していくかが難しい課題となっています。自由の拡大、公正・安全安心の確保、プライバシイの保護という、ともすれば、矛盾相剋しがちな3つの価値の高度均衡、即ち三止揚を実現するために、経営管理・運営(Management)、行動規範・倫理(Ethics)、法制度(Law System)、情報通信技術(Technology)の4者によるMELT—up が不可欠です。
SCAT が、今後とも、このような広い視野の中で、人と情報が調和するエコシステムの構築に貢献されることを祈念しております。
SCAT30周年を祝して -ICT 研究のパラダイムの変革- 公益財団法人 電磁応用研究所 理事長 富永 英義 (早稲田大学名誉教授)

公益財団法人 電磁応用研究所
理事長 富永 英義
(早稲田大学名誉教授)
SCAT の設立の目的を紐解くことにする。
昨今の公的研究資金の応募要項にはIoT、AI、5G、8K のキーワードにあふれている。それらの複合または融合した組み合せによる課題も多く見受ける。
30 年前の研究課題には、無線と有線、固定と移動、放送と通信、ISDN とインターネット、光やFTTH、機能IC チップなどの単語がキーワードとして並んだ。
この時期、電電公社は電子交換機の本格導入がなされ、さらにそれを進展させるINS 網の商用実験がなされていた。一方、ベル研が開発したコンピュータ通信のOS(UNIX)が市場に現れ、新たなコンピュータネットワークの開発においてNTT のデータ通信網の解放が必要となった。
すなわちICT(情報通信技術)なるパラダイムが生まれた。
それまで電気通信技術の研究の頂点は、電気通信研究所、放送技術研究所、電波研究所にあった。これらの研究所と産業界が一体となり、国が主導する研究チームとしてITU、ISO、IEEE などに参加する日本人の数は主催国に次いで群を抜いて多かった。
30 年前までは、NTT や参加企業の電気通信技術の研究費の原資は電話料金収入の4%程度が目標であったが、大学が企業と同じような契約による研究開発の一翼を請け負うには難があった。
公社の電気通信研究所の使命は国産の電話交換網や無線機器を開発して電気通信インフラの整備に寄与することであった。研究視点は『何をどのように作るか:How to make』であった。民営化後は民間企業として競争するために研究視点は社会インフラとして通信網を維持、管理、開発するために『何をどのように使うか:How to use』にある。
規制の緩和は、大学での研究活動の活性化を求めることになった。
しかしながら、研究に携わる人材を大学の組織に置くには、研究活動を事業化して財政的な安定を図る必要がある。日本の大学の制度では、収支バランスを授業料や施設費を学納金収入(学生が納める)で賄うしかない。実務的教育・研究を疎かにできない医学部の学生には群を抜いた学納金が必要となる。
国公私立の大学の教育・研究業務の経常経費は大幅赤字である。私立大学においては、持続的経営を担保するために国の補助金が支給されている。国立大学においては、学納金は国庫に入金され、教育・研究の経常経費は国の機関としての財務処理をしている。国の機関としての大学は獲得した予算の執行をするので、収支バランスの視点は乏しいものであった。
通信産業の自由化の動きと同期するかのように、文部科学省は大学における教育・研究環境の改革の施策が、次次と打ち出され、多くの議論があった。
それまで、産業界の研究開発部門で行っていた研究課題を大学の研究室でも行うことが必然となった。制度面で特筆できるのは国立大学の法人化と研究機関に独立研究大学院の機能をもたせることであった。NICT やNII の組織がそれに対応する。
大学で社会が必要とする研究を行うことができる競争的研究資金の制度が盛んになったのは今から10 年ほど前からである。30 年前に、NTT とKDD の出捐により財団法人SCAT が創設されたのは先端的なICT の研究の着手を支えるのに有効であった。
1980 年代、アナログ技術の時代には、諸外国でも国際的な規制が不可避であった電気通信事業も、コンピュータと通信の融合がもたらす規制緩和による技術開発の地球的視野による競争と協調の道を歩んできている。
1993 年9 月、米国クリントン政権はNII(米国情報基盤構想)を提唱し、翌年、ゴア副大統領がITU の第1 回世界電気通信開発会議においてGII(Global Information Infrastructure)へと変化した構想を表明した。これは、ICT における経済戦争とも呼べる事態であったが、日本社会での報道や認識はほとんど無かったといえる。
今、ICT 機能と融合することで実現するスマート社会のパラダイムに直面している。
次の30 年に向かって、一般財団法人SCAT が脱皮した存在として発展することを願う。
超高速フォトニックネットワーク 開発推進協議会(PIF)の活動を振り返る 東京大学名誉教授 青山 友紀

東京大学名誉教授
青山 友紀
我国では1981 年に32M/100Mb/s 光伝送システムが初めて導入され、その後400Mb/s、1.6Gb/s、10Gb/s、100Gb/s と高速化し、さらにWDM,マルチコアファイバ技術などによって100Tb/s/ファイバからPeta b/s/ファイバの伝送容量の実現に向けて研究開発が推進されている。
光通信技術発展の流れの中で、1990 年代に入ると、インターネットが社会に普及し始めたが、それまでの電話ネットワークの拡大に対応する目的で導入されてきた光ファイバ通信方式をそのまま適用するだけではインターネットの性能が制限されるおそれが生じてきた。すなわち、従来の光通信技術の進歩は2 地点間の光伝送速度を高速化するためのデバイス技術、伝送技術に焦点が当てられていたが、それによる光パルスの高速化に電子回路によるインターネットルータの処理が追い付かず、エンドツーエンドのパケット転送速度が頭打ちとなるのである。インターネットへの適用を考慮した技術的課題を調査し、その課題を解決する研究プロジェクトを産学連携で進める政策を当時の郵政省に提案し、1999 年11 月より郵政省に「フォトニックネットワークに関する勉強会」を設置し、座長を務めた。2000 年にまとめられた報告書にはフォトニックネットワークの調査研究を推進する産学連携の非営利団体の設立が提案され、2001 年2 月に非営利団体「超高速フォトニックネットワーク開発推進協議会(PIF: Photonic Internet Forum、事務局:SCAT)」が設立され、会長に就任した。
PIF のミッションはインターネットの普及に伴う爆発的な通信需要に対処するための全光技術による超高速大容量のネットワーク(陸上、海底の長距離コアネットワーク、メトロポリタンエリアネットワーク、光加入者系FTTH/FTTC を含む)を構築する「超高速フォトニックネットワーク」の研究開発の促進を図るため、その技術の研究開発に関して、企業・大学・研究機関や有識者、国の機関の関係者が幅広く糾合して国内外の技術開発動向の調査、協議会参加メンバの交流、広く一般への普及啓発、研究開発すべき重点テーマの提案、などを推進し、我国のみならず世界の情報通信技術の発展に寄与することである。その活動が評価され、2003 年の電波の日に会長が代表して総務大臣表彰を受賞することができた。
主な活動を要約すると下記の通りである。
(1)フォトニックネットワークの研究開発課題の提言
我国の産学が共同して研究開発すべき課題を検討した。その報告をベースに2002 年1 月に「フォトニックネットワーク革命」という書籍をSCAT より発行した。その中で示された2001年から10 年間のフォトニックネットワーク技術の研究開発のロードマップの図は世界で初めての提示であり、海外でも広く引用された。議論の結果の研究課題を具体的に解決するために総務省が提示すべき方策を検討し2001 年にスタートしたe-Japan 戦略、その後継として2004 年にスタートしたu-Japan 戦略の光通信領域の策定にも貢献した。
(2)海外調査団の派遣と日中韓の交流
2001 年に北米調査団、2003 年に中国調査団、2005 年にEU 調査団、2010 年に米国調査団を派遣した。この調査によって、その国や地域の光通信や光デバイス研究開発に関する最新情報を入手するとともに、人脈の形成にも大きく貢献し、その後の交流の起点となった。
また韓国にはPIF と同様な非営利団体としてKOIF(Korean Optical Internet Forum)が、中国もOIFC(Optical Internet Forum of China)が発足し、これら3 団体が交流するための議論が2004 年にスタート。その後、3 機関の交流に関する覚書の締結の式典が2006 年9 月に北京で開催され、青山PIF 会長、Minho Kang KOIF 会長、Mao Qian OIFC 会長がサインした。この覚書をベースに各フォーラムの年次総会で自国の光技術の研究開発状況を紹介する講演者を相互に派遣することが行われ、KOIF とは現在も継続されている。
(3)フォトニックネットワーク技術の普及啓発活動
PIF は会員、および非会員を対象とした講演会やセミナー、チュートリアルを年に数回開催しフォトニックネットワークや広く光技術全般の普及啓発活動を進めてきた。2006 年の総会ではPIF 創立5 周年記念シンポジウム、2011 年にはPIF 創立10 周年記念講演会を盛況に開催した。さらに、光通信の国際会議OECC, PS, COIN, などに対する協賛やサポート、また毎年日本で開催されるiPOP に対しては第1 回より継続して協賛しその開催を支援してきた。
フォトニックネットワークに関する国際標準化の動向調査や標準化活動の支援を進めた。
(4)PIF の今後の課題
光ネットワークに関する世界のビジネス競争は激しさを増しており、我国の産業界においてそのビジネスから撤退する企業も増加している。その理由は大量生産に必要な設備投資と徹底したコストダウンが必要となり、また長期の研究開発に要する多額な研究開発費の必要性により厳しい経営に直面しているからである。
しかし、光デバイス、光通信の領域における我国の技術力は現在では世界を先導する位置をキープしており、今後その力が弱まるのは我国の産業界、学界、ひいては社会において極めて問題であり、今後も我国がPIF を中心にフォトニックネットワーク技術の発展に向けた活動を維持発展し、それを総務省、経産省、文科省が協力して支援することが極めて重要な課題である。
研究助成を頂いての研究活動を振り返って 放送大学 東京渋谷学習センター長 酒井 善則 (東京工業大学名誉教授)

放送大学 東京渋谷学習センター長
酒井 善則
(東京工業大学名誉教授)
私は1974 年に大学の博士課程を修了して、当時の電電公社(NTT)に入社し、電気通信研究所画像通信研究部に配属されました。そこで13 年余にわたって従事したのは画像そのものの研究ではなく、画像通信を対象としたディジタル伝送方式、ネットワーク、さらには通信会議システムなどの開発でした。当時は電話全盛の時代で、私の研究開発成果でNTT が大きな利益を上げることはありませんでしたが、後から考えると、殆どは現在のIP ネットワーク時代の先駆けとなる技術でした。
1987 年に東京工業大学の助教授に就任したとき、それまでやっていた巨額の研究費を使ったシステム開発はとても出来ないため、何をやるか悩みました。米国の大学教授より、大学では研究費を集めて博士を多くだせば、後は何をやってもいい、と言われたことを思い出します。研究室発足2 年後の1990 年には、留学生中心に3 人の博士学生がいて、テーマ選定に一刻の猶予はありませんでした。そこでNTT 時代の研究をもとに、将来の映像メディア時代を見据えて、映像のためのネットワーク、画像を介したマンマシンインタフェースを3 人のテーマとして選びました。とはいうものの、科研費などの公的研究費は、研究費が不足している教員より、研究費獲得実績の大きい教員に有利になり、当初は研究費獲得に大変苦労しました。その時にSCAT の存在を知り、マンマシンインタフェース、やや時間をおいて映像伝送の2 つのテーマで2 回に渡り研究助成を頂けたことは、大変ありがたく、感謝しております。
助成頂いた一つのテーマは身振りによる機械制御で、NTT 時代に開発した通信会議装置でマンマシンインタフェースの開発に苦労したことがテーマ選定のきっかけになりました。身振り手振りの理解が中心で制御対象は何でもよかったのですが、SCAT だから通信網制御を対象とした方がよいと思って、そのようなタイトルとしました。画像処理、意味理解も含まれていたため、博士論文にもなりやすかったことも理由でした。後年、色々な助成金の審査側になると、若い人が同じ研究を、助成金の性質に合わせたネーミングで申請してくるのを見て、自分の過去を思い出します。もう一つのテーマはインターネット上の映像伝送で、助成頂いた時期には符号化と伝送を組み合わせた品質制御に発展していたと思います。私は東工大在職24 年強で、研究室としては30 人位、私が主査となったのは25 人位の課程博士を世にだしましたが、この2つのテーマおよびその関連でも、10 人近い学生が博士号を取得したと思います。
研究費獲得は大学教員にとって極めて重要で割く時間も大きくなります。米国のノーベル賞受賞者の学者も、自分の仕事の大部分は研究費獲得だ、と言っていました。SCAT は既に多額の研究費を獲得して実績のある教員より、まだ実績が小さく意欲的な教員に対して助成した方が、同じ金額でも効果は大きいのではないかと思います。
SCAT発足の経緯と期待 YRP研究開発推進協会会長 甕 昭男

YRP研究開発推進協会会長
甕 昭男
我が国において昭和60 年4 月に電気通信制度の歴史的な改革が行われ、従来独占であった電気通信事業が自由化されるに至り高度情報社会形成の主役を担う新しい電気通信サービスは競争原理を軸とした広範な創意にもとづいて提供されることとなった。このような流れの中で高度な電気通信システムをいかに社会に円滑かつ効果的に定着させて高度情報社会への移行を実現させていくかという総合的な電気通信政策が重要な課題となっていた。
その中で特に技術開発体制の確立と我が国の電気通信技術の維持・発展していくための施策がもとめられることとなった。そこで電気通信行政を所管する郵政省は高度情報社会形成にとって電気通信技術開発の重要性と同時に電気通信技術が社会に与える影響の大きさに鑑み、新しい電気通信制度下における総合的電気通信技術開発政策のあるべき姿の調査検討を行うこととし大来佐武郎国際大学学長を座長とする有識者による「電気通信に関する技術開発政策懇談会」を昭和59 年9 月に設置し2 年間の調査審議を経て最終報告をまとめた。郵政省ではその懇談会の報告を踏まえて電気通信技術審議会に「電気通信技術に関する研究開発指針」を諮問し答申を得て、電気通信フロンテア技術等基礎的・先端的技術の研究開発の推進、基盤技術促進センターによる出融資、各種税制、標準化、地域振興などの施策が次々と打ち出された。
小生はこの時期に郵政省通信政策局で技術開発企画課長として電気通信行政のうちの技術戦略を担当していたことから財団法人テレコム先端技術研究支援センターの設立に係ったりその育成に関与したのでその状況と当法人への期待がどのようなものであったかについて記憶が薄れている中ではあるが思い出しながら述べることとしたい。
前述したとおりに我が国の情報通信環境は昭和60 年のNTT の民営化と電気通信事業の自由化により大きく転換したがその研究開発の弱体化や国際競争力の低下が生じるのではないかとの懸念が心配された。その対策として国の研究基盤の強化、研究助成の充実、国際的共同研究の強化などを図るべく戦略として、電波研究所の通信総合研究所への改組と電波以外の研究分野の充実、基盤技術促進センターの助成による㈱国際電気通信基礎技術研究所の創設、ISDN 国際共同研究プロジェクトの創設、YRP 研究開発推進プロジェクトなどリサーチパーク支援などが遂行された。
このような情報通信分野の研究開発の多様化や多角化に対処する施策が広範に進められることとなったが産学官の連携の強化についてもっと充実すべしとの声が大きくなってきたことから「電気通信技術に関する研究開発指針」に示されている産学官の研究支援体制の整備充実について関係者間で機運が高まってきた。このような背景のもと、昭和63 年10 月3 日にNTT、KDD、NHK、通信機器メーカー等18 名の社長等が設立発起人となってテレコム先端技術支援センター(SCAT)が設立され、約2週間後の10 月26 日に郵政大臣より財団法人設立が許可されるに至った。
SCAT の設立は日本の情報通信分野での研究開発の重要性に鑑みその活躍が大いに期待され、その初代会長には経団連の推薦で武田新日本製鉄株式会社会長、専務理事には塚本郵政省通信総合研究所所長が就任され、理事に通信事業者、通信機器メーカなどが就任し錚々たる役員体制となって昭和63 年10 月スタートした。
情報通信技術政策を推進する立場にいた小生としてはこの時の関係者による期待の大きかったことを鮮明に覚えている。是非、近年の我が国の研究開発の国際的プレゼンスの低下している状況を何とか打破していただくべくSCAT 設立当時の関係者の熱い思いを思い起こしていただき活動していただくことを祈念して30 周年に当たっての挨拶とします。
SCAT創世期を回顧して テレコム先端技術研究支援センター 初代専務理事 塚本 賢一
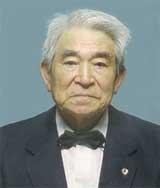
テレコム先端技術研究支援センター
初代専務理事 塚本 賢一
郵政省三浦審議官より新しく発足予定の「テレコム研究開発振興センター(SCATのこと)」の専務理事への転任打診があったのが、昭和63 年5 月11 日のことで、一両日中に返答をとのことである。1か月前の4 月8 日に郵政省電波研究所(RRL)が通信総合研究所(CRL)に名称変更し、その初代所長を拝命したばかりであったが、翌日決意して承諾の返事をした。6 月10 日にCRL退職の辞令を受けてからは、通信政策局 甕技術開発企画課長から逐一財団設立へ向けての準備状況の情報提供を受けながら、暫時待機状態を続けた。
内幸町の第一勧業銀行本社内の一室を借用しての支援センター準備室が発足したのは9 月1 日である。当初の陣営は真船室長以下5名であったが、その後次第に増員された。
10 月3 日に東海大校友会館に於いて会長・武田豊氏以下18 名の出席の下、発起人会が開催され、設立趣旨、寄附行為、事業計画の承認がなされた。10 月26 日の免許状授与式は午後2 時から郵政省通信政策局長室で行われ、さらに10 月28 日には設立登記手続きが完了し、財団発足となった。11 月15 日に虎ノ門一丁目の第12森ビル3 階への事務所開設が実施され、準備室からの移転が完了した。この時点での組織は常勤13 名、役員11 名、評議員21 名の体制であり、内部は事務局長の下、企画部、調査研究部の二部構成であった。常勤職員は郵政省からの要請によりNTT、KDDをはじめとする主要企業からの交代制で出向派遣されてきた技術能力と国際感覚豊かな人材で構成されていた。
12 月12 日には第1回理事会が新事務所の会長室で、また12 月16 日には同じく会長室で初の評議員会が北原議長の下で開催され、専務理事の私が進行兼説明役を務め、実質私の第2の人生披露の日となった。続いて会議室で約70 名参加での事務所開設披露パーティが、奥山郵政事務次官の祝辞、岩崎NTT代表取締役の乾杯、山根新日本製鐵副社長の中締めで賑やかに行われた。
平成元年5 月29 日、ストラーダ新宿にて第1回テレコム技術情報セミナーが財団主催で開催され、約90 名の参加で最初の対賛助会員サービスイベントを成功裡に終わらせることができた。8 月25 日、当事務所会議室で第1回テレコム技術情報懇談会開催。9 月5 日、郵政省飯倉別館特別室で広帯域ISDN推進協議会が秋山稔東大教授の会長選出で開催、さらに10月27 日に当財団事務所会議室で同推進協議会のシステム分科会が開催された。
11 月9 日~10 日には、お茶の水ヴォーリスホールで第1回電気通信フロンティア研究国際フォーラムが開催され、第1 日目は国内外から会場一杯の200 名近くが参加した。セッション終了後、会場を山の上ホテルへ移してのレセプションでは、大石郵政大臣と熊谷組織委員長の挨拶の後、約150 名会場一杯で進行し、7 時半頃終了した。翌日の第2 日目も盛況裡に終始し、最初の重要な国際イベントを成功裡に遂行させることができた。後日判った事であるが、この第1 日目は奇しくもベルリンの壁崩壊という20 世紀屈指の歴史的イベント発生の日。この偶然の一致はこのプロジェクトの重要性を高く評価する暗示のように思えた。
11 月17 日(金)~18 日(土)に財団初の秋季旅行会が実施された。25 人乗りバスを借り切り、14 名参加で静岡県の寸又峡、浜名湖方面への紅葉狩りが行われ、職員慰労のイベントとなった。なお職員慰労の旅行会は、その後毎年実施される事となった。
12 月8 日には、午後3 時より通政局長室で、中村通政局長、大越東大教授の対談が約1 時間20 分行われた。これが翌年の平成2 年1 月発刊の機関誌「SCAT LINE」創刊号で武田豊会長の挨拶に続いてトップ頁を飾る記念記事となった。
財団発足第1年目の主要行事は以上のとおりであるが、この間、財団活動への参画と活動資金確保の目的で多くの企業を訪問し、賛助会員加入勧奨を行った。
翌年の平成2 年7 月19 日の第8回理事会で新日鉄会長の齋藤裕氏が当財団第2代会長に選任された。
10 月23 日~24 日には、郵政省飯倉別館にて第2回電気通信フロンティア研究国際フォーラムが約500 名の参加の下、江崎玲於奈博士の特別講演も含めて盛況裡に開催された。その後も毎年1回、会場を変えながら開催され、財団はその事務局運営を担当した。
翌平成3 年9 月24 日には、当財団会議室で初の研究助成審査委員会が猪瀬博先生はじめ7名の委員出席の下に開始され、財団の最重要ミッションがスタートした。
平成5 年4 月12 日に新宿御苑近くの小池ビル6階への事務所移転が行われ、実質1/3への経費削減が達成された。当日は皇太子納采の佳日でもあった。
約6年半に及ぶ勤務を終えて、私は平成7 年3 月末をもって財団を辞任し、郵政省主導で新発足の(株)次世代デジタルテレビジョン放送システム研究所(DTV Lab)の代表取締役へ転任することとなり、そこでの職務を無事果たすことが出来た。
今回30周年を迎えるに当たり、在任中に各方面から頂いた御指導・御協力に感謝するとともに、当財団の益々の発展を希うものである。
古き良き時代 テレコム先端技術研究支援センター 元専務理事 畚野 信義

テレコム先端技術研究支援センター
元専務理事 畚野 信義
1997年7月初め、家内とヨーロッパ旅行から帰宅すると郵政省から何度も電話があったと息子から聞き連絡するとSCATの専務理事に既に就任していたことを知らされた。前年秋に東大の寄付講座(伊藤忠、Global Climate)の任期が終わり、これで自由になったと、最初の飛行機の到着の地だけ宿を予約して、パスポートとユーロパスだけを持って6-8週間ヨーロッパを自由に旅することを始めて、それが2回目だった。何か月か前、当時の甕技総審から「近年日本のR&D予算が急速に増えて来たが、これの支援をキチンとやる必要があるので畚野さんをスカウトしたい」と言われ、やらして貰うと返事したがこんなに早く事態が動くとは思っていなかった。郵政省で担当の松井さんやSCATの前任の三浦さんには大変迷惑をお掛けしたが、着任すると今度は私が驚く番だった。
(財)テレコム先端技術研究支援センター(SCAT)は、1988年10月26日に設立後、NTT・KDDの5ケ年度にわたる出捐等により、1992年度には47.5億円の基本財産が形成されていた。設立当時は銀行利子が数%/年にも上り、この50億円近い基本財産の運用利益で研究の支援等をやっていたが、その後利率がどんどん下がり、家賃節約のため虎ノ門から新宿御苑へ逃げて来たようだが、私が就任した時には銀行利子はタダ同然になり、財団の最重要事業である研究の支援さえが困難になっていた。基本財産を食う(減らす)訳には行かず、これではならじとイロイロ考え、翌年度の理事会には「撃って出ます」と宣言して、田中(征治)技総審と図り、次々と新しい研究テーマ発掘の委員会を郵政省が設定し、SCATが運営の支援(委員等への連絡等の事務やお茶代、旅費、謝金等必要経費の支出)をした。何でそんなものにナケナシの金をという反対もあったが、それらの中から量子通信(コンピューター)、タイムスタンプ等のプロジェクトが陽の目を見た。立ち上がった研究プロジェクトの推進をSCATが行うことで収支が改善され、人体(特に脳)への電波の影響の調査のように大型で長期にわたるテーマも出て来て、SCATの収入は雪ダルマのように増えて行った。この間8階建てビルの6階1床から5、6、7階の3床に増やし、立派な会議室も自前で持つことが出来た。職員も企業からの出向者、契約社員等多様であったが大きく増員出来た。周囲からのタレコミがあったのか時間外に労基局の予告なしの調査が入るなどのハプニングもあったりしたが。
私はCRL(通信総合研究所),ATR(国際電気通信基礎技術研究所),TRMM(熱帯降雨観測衛星:日米共同衛星計画)等の大きな組織やプロジェクトに関わり、人材の重要性を身に染みて感じているが、SCATのような比較的小さな組織でもやはり人がカギであった。
私が着任した時は大矢君が本省から番頭の役割で出向していた。私は白紙の状態で着任したがお蔭で直ぐに全体像や問題点を把握し、動き出すことが出来た。しかしこの頃人事院はこのような若い人材を霞が関から関連団体へ出向させることは特別な理由がない限り認めないと言い出した。そこで特別な理由を探すことになった。
冷戦時代世界中の深海に展開していた米原子力潜水艦は一旦緩急あると海面に浮上し、上空に展開するNAVSTAR衛星システムからの電波を受信し、瞬時に自身の正確な位置を算出し、予め予定されたターゲットに向かって正確にミサイルを打ち出すシステムが整備されていた。冷戦時代が終わりこれを民間も利用出来るようになったのがGPSである。しかし本来軍用であることから非常事態時には民用へ提供される位置精度等が意図的に劣化される等の難点があり、実際に湾岸戦争等でそのような事態が起こっていた。またこのような重要な仕組みをアメリカに頼る(握られる)ことを問題とし、ヨーロッパやロシア、中国等で独自のシステムを持とうとする動きが始まっていた。当時のクリントン大統領から小渕首相へ日本はGPSシステムを利用するようにと要請が来ていた。そんな事情で我が国が独自のシステムの検討を霞が関(郵政省)で行うのはデリケートであり、実用システムの検討を研究所(CRL)で行うことも適当でないのでSCATで行うという理由が認められ、南君の出向が実現した。彼の次に藤本君が来てくれた。上記したような新プロジェクトの相次ぐ創設には、この二人の本省との密接な連携が大きな力となった。SCATの日常業務の実施では賛助企業からの出向の技術者が中心であった。プロジェクトの増加に伴い新しい企業からの出向をお願いした。またそれら企業には優れた人材を強く求め、問題のある人には交代して貰ったこともあった。暫くするとあそこに頼めばよい仕事をしてくれて安心できるという評判が拡がり、次々と依頼が舞い込むようになって行った。
2001年2月、その頃毎年1週間ほど行くことにしていた八幡平のスキー場のホテルへ「2000年度限りで基盤技術研究促進センターの制度が廃止されるので、ATRを頼みたい」という田中技総審の電話があり、私のSCAT時代は急に終わることになった。

